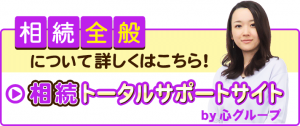- トップ
- ブログ
ブログ
国庫帰属制度の申請手続きについて
皆様、お久しぶりです!
弁護士法人心の林です。
前回は、国庫帰属制度の利用状況等について解説してきました。
今回は、それに引き続き、国庫帰属制度の申請手続きについて解説していきたいと思います。
国庫帰属制度の大まかな流れとしては、以下の5段階が設定されています。
① 申請者
② 添付書面
③ 法務局における内部審査
④ 審査結果
⑤ 負担金の納付
以下解説していきます。
1 申請者の選定
⑴ 原則
国庫帰属制度の申請者としては、基本的には相続等によりその土地を取得した者と考えられています。
ここで、代理人が申請者になることができるのかについて問題となりますが、法定代理人(成年後見人等)であれば申請者となることができますが、任意代理人(弁護士や司法書士等の専門家)は申請者となることができないとされていることに注意が必要です。
もっとも、申請書類の作成代行を行うことまでは禁止されていないので、不安な方は経験豊富な専門家に申請書類の作成代行を依頼するのが良いでしょう。
⑵ 例外
ア 共有者がいる場合
国庫帰属制度は土地の所有権を国に移転させるという制度ですので、共有者が居る場合には、他の共有者全員を含めて申請することが必要とされています。
そのため、一人でも国庫帰属に反対をしている方が居る場合には、申請自体ができないということになります。
イ 法人が主体となること
法人は相続等によって土地を取得することは通常考えられないため、原則として国庫帰属制度の申請者となることはできないと考えられています。
もっとも、法人が共有者として登記されている場合に、他の自然人が相続等により土地を取得した場合には、法人も申請主体となることができるとされています。
このような場合には、自然人までも申請を妨げられることになってしまうという結果を避けるための措置がしかれているという事になります。
2 添付書面
添付書面については、少し複雑なので、次回に解説を行います。
3 法務局における内部審査
⑴ 管轄法務局
国庫帰属制度の管轄法務局は、各土地が所在する場所を管轄する法務局とされています。
もっとも、支局や出張所は管轄法務局となることはできず、それぞれの所在地を管轄する法務局の本局に管轄があるとされています。
例えば、岐阜の高山にある土地については、通常は岐阜地方法務局の高山支部に不動産登記の申請を行いますが、国庫帰属制度の申立ての場合には、岐阜地方法務局の本局に申立てを行う必要があるという事です。
⑵ 標準処理期間
国庫帰属制度の申請を許可するか否かについて、法務局は平均して8カ月程度で審査結果を伝えるとの運用を行っています。
これは、申請された土地の現在の状況や、国家による有効利用の可能性等を検討するために設けられている期間であり、それを審査するのに、おおよそ8か月かかるという事を示しています。
4 審査結果
⑴ 承認
法務局は、国庫帰属の申請を承認することとした場合には、承認したことを通知する必要があるとされていて、この承認の通知は負担金の納付の通知と併せて行うこととされています。
⑵ 却下
法務局は、次のいずれかの事由に該当する場合には、申請を却下することができるとされています。
この時の却下とは、申請権者ではない等の形式的要件を欠いている場合を指します。
ア 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき
イ 承認申請者が必要事項を記載した承認申請書を提出しないとき
ウ 審査手数料を納付しないとき
エ 正当な理由がないのに、法務大臣の事実の調査に応じない時
このような事項があると、そもそも審査すらできないため、必ずこの点の確認は行うようにしましょう。
⑶ 不承認
法務局は不承認事由がある場合には、申請を不承認とすることができるとされています。
(不承認事由については、次回以降に詳しく解説します。)
この不承認に対しては、行政不服審査や行政訴訟を行うことができるとされていますので、問題があると考えるときは不服を申し立てるのもありかもしれません。
⑷ 取下げ
申請自体は取り下げる事ができます。
ただこの時でも、審査手数料は帰ってこないため、注意が必要です。
5 負担金の納付
国庫帰属の申請が承認されたときは、負担金を納める必要があります。
この負担金は、基本的には一筆について20万円とされることが多いようですが、当該土地を管理するのに、草刈り等の管理が必要となる場合には、面積に応じた金額の納付が必要となるとされています。
そのため、広大な土地を国庫帰属させるには、それに対応できるだけの現金が必要になりますので、注意が必要です。
今回は、国庫帰属制度の大まかな申請手続きについて解説していきました。
次回は、添付書類及び不承認事由について解説していきたいと思います。
それでは、また次回お会いしましょう。
国庫帰属制度の概要について
皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
今回からは、令和5年から始まった「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていきたいと思います。
1 制度趣旨
「相続土地国庫帰属制度」は、土地を相続により取得した場合に、一定の要件に該当する場合には、その所有権を国に帰属させることを認める制度になります。
この制度ができた背景としては、人口の都市部への集中を契機として、自身にとって不要な土地を相続することへの負担(固定資産税や管理費等の諸費用)が、所有者不明土地の拡大の一端を担っているという指摘を受け、それを解消するために所有者に任意に所有権を放棄することを認めたという点にあります。
2 現在までの運用状況
令和5年の運用開始から令和7年1月31日までの速報値に基づく統計を参照(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html)してみます。
⑴ 申請件数
申請件数の推移としては、現在までに「3343」件の申請が行われています。
運用開始から1年半と少しの期間に3000件以上の申請がなされていることからして、不要な土地を手放したいというニーズは今後も増えていくことが予想されます。
また土地の属性ごとの分類では、「宅地」が1188件、「田畑」が1258件「山林」が520件とされています。
⑵ 帰属件数
これに対して、実際に所有権が国に帰属した件数としては、全体で「1324」件となっており、約39%の割合で申請が認められている計算になります。
また土地の属性ごとの分類では、「宅地」が518件、「田畑」が405件、「山林」が63件とされています。
この値から、「宅地」は約43%、「田畑」が約32%、「山林」が約12%の割合で認められていることが分かります。
このことから、一番需要が高いと思われる山林の所有権帰属には、高いハードルがあることが推察されます。
3 申請前の相談の活用
現状の運用状況の評価としてはこのような状況ですが、申請前にどの程度の割合でご自身の申請が認められるかを推察することができる方法があります。
それが、法務局の相談窓口の活用です。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html)
法務局では、完全予約制で手放したい土地の国庫帰属に関する申請の相談を受け付ける事とされています。
この相談では、一般的な質問にとどまらず、申請を行った場合の見通しや、申請書類の不備の確認など、個別具体的な相談にも乗ることができるとされています。
そのため、実際に申請を行う前には、必ず法務局への相談を行った方が、より正確な見通しを立てられるようになるといえるでしょう。
以上です。
今回は、「相続土地国庫帰属制度」について、制度趣旨の説明と現状についてお話をしてきました。
次回は、実際に「相続土地国庫帰属制度」の申請手続きのご説明や添付書類の解説を行っていきたいと思います(内容によっては、二回に分ける可能性もあります。)。
それでは、また今度お会いしましょう。
少年事件の手続きについて
みなさま、こんにちは!
今回は、少年が逮捕・勾留されている場合の少年事件の手続きについて解説していきたいと思います。
少年が逮捕・勾留されている場合の少年事件の手続きには、大きく分けて3つの段階が考えられます。
その段階とは、①逮捕、勾留段階②家裁送致段階③審判段階です。
①の逮捕、勾留段階では、成年の刑事事件と同様に、逮捕から72時間以内に検察へと送致され、勾留手続きが行われた場合には原則10日間の身体拘束が行われることになります。
この逮捕、勾留段階では、警察官や検察官から事件に関する取り調べ等の捜査が行われる事になります。
少年はこの間に警察の留置施設もしくは少年鑑別所に身体拘束されることになるため、心身に大きな負荷がかかることになります。
そのため、弁護人やご家族の方(面会が許可されている場合)が定期的に会いに行くことでそのストレスを和らげる必要があります。
②の家裁送致段階では、家庭裁判所の調査官による面接が行われることになります。
検察は、少年事件については、原則として全件を家庭裁判所に送致することとされています(全件送致主義)。
全件送致主義が取られている背景としては、非行を行った少年はたとえ軽微な犯罪であったとしても、重大な犯罪を行ってしまう危険性があることに鑑みて、裁判所が後見的に少年に潜む問題点を指摘し、更生を行っていく必要があると考えられている点にあります。
一定の軽微な犯罪については、調査官による面接も行われない「簡易送致」という類型もあるものの、ほとんどの事件は家庭裁判所に送致されます。
この調査官による面接では、少年の非行に関する事実のみではなく、少年の養育環境や思考に関する傾向なども調査されることになり、そこで調査された事実が裁判官に報告され、審判の前提となるので、とても重要な手続きであるといえます。
③の審判段階では、裁判所が少年に対して、⑴保護観察⑵少年院送致⑶不処分、審判不開始決定のいずれかの決定を行います。
審判手続きを行う前に裁判所から審判期日が設定され、その期日において、裁判所から少年や親族に対する質問が行われます。
この段階では、裁判所が審判を下すうえで重要な質問が行われるため、付添人を選任して対策を行っておくことが望ましいです。
この審判期日でも、非行事実に関する質問のみでなく、養育環境等に関する質問までも行われるため、少年のみではなく、親族の方も今後どのように少年を養育していくのかについて考えておく必要があります。
このように、少年事件の手続きは、少年の今後の更生を考えていく構成となっているため、当事者全員が少年の今後の更生を考えておくことが望ましいといえるでしょう。
それでは、今回はここで失礼いたします。
嫡出でない子の相続分について
皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
今回は、嫡出でない子の相続分についてお話していこうと思います。
1 平成25年の改正前民法の規定
平成25年12月11日より以前の民法では、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が存在していました。
しかし、この規定は、子供にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないとの理由で、最高裁平成25年9月4日決定により、違憲とされました。
その結果、現在では、非嫡出子の相続分を2分の1とする規定はなくなっており、嫡出でない子も嫡出子と同一の法定相続分を持つとされています。
2 所有者不明土地の問題
他方、最近よく耳にするのが、所有者不明土地の問題です。
この問題は、何世代にも渡って、相続手続きがなされない事で、誰が相続したのかが判別が困難であったり、所有者として登記されている者の所在が分からない事が原因で発生しています。
この問題を解決するために、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に名義変更を行わなければ、10万円以下の過料が課されることとされました。
そのため、今後は何世代にも渡って相続手続きがされていない土地についても遺産分割が行われる可能性が出てきたのです。
3 嫡出でない子の相続との関係
何世代にも渡って相続されていない土地建物について遺産分割を行おうとした場合、平成25年12月5日以前に発生した相続についても解決していく必要がある場合があります。
その際、嫡出でない子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされるのか否かが問題となります。
この点について判断した審判例では、平成13年2月に発生した相続についても、最高裁平成25年9月4日決定が指摘するような社会状況があったことを指摘し、嫡出でない子と嫡出子の法定相続分は同一として判断していくとしました(那覇家審令和5年2月28日)。
そのため、今後も平成25年以前の相続手続きを行っていく際に、嫡出でない子の相続分をどのように考えていくのかという点について、この審判例を引用して考えていくという場面が増えるかもしれません。
なお、あくまで一審判例ですので、必ず平成13年2月以降に発生した相続について嫡出でない子の法定相続分が嫡出子と同一であると判断されるわけではないという点については注意が必要です。
4 このように、嫡出でない子との間の相続に関する問題点は複雑化する可能性がありますので、手続きを行う際には必ず弁護士に相談するようにすると良いでしょう。
それでは、また次回お会いしましょう。
海外に居住している相続人と印鑑証明書について
皆様お久しぶりです。
弁護士法人心、弁護士の林です。
今回は、外国に居住している方との間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するとき、印鑑証明書に代わる書類をどのように用意していくのかという点について解説させていただきます。
1 遺産分割協議書を使用するには、印鑑証明書も添付する必要がある
相続手続きは、「遺産分割協議書」を作成して終わりというわけではなく、銀行口座の解約を行ったり、相続登記を行ったりする必要があります。
そして、銀行口座の解約や相続登記を行う際には、「遺産分割協議書」と一緒に「印鑑証明書」を添付する必要があります。
この「印鑑証明書」は、遺産分割協議書の印影が実印の印影であることを証明する書類であり、この書類を添付することで、印鑑証明書の名義人の意思による押印があったことを推認しています。
2 海外在住者の場合の「印鑑証明書」
「印鑑証明書」は、名義人が居住している地域の市役所や町役場等で発行されますが、海外居住者の場合には、日本国内に居住していないため、この「印鑑証明書」が取得できません。
このような時には、どのようにして銀行口座の解約や相続登記を行っていくのでしょうか。
その方法として、「署名証明書」を発行してもらう事が考えられます。
3 「署名証明書」とは
「署名証明書」とは、「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。」(外務省HPhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html参照)。
この署名証明書を発行するには、海外在住の相続人が日本国の領事館等に出向き、署名証明書の発行を依頼する必要があります。
そして、実際に領事の面前で、遺産分割協議書に署名を行う必要がありますので、必ず書類にサインをしていない状態で領事館に持っていくようにしましょう。
4 署名証明書の種類
署名証明書には、「形式1(遺産分割協議書と証明書を割印するタイプ)」と「形式2(証明書を発行するのみのタイプ)」があります。
「署名証明書」は遺産分割協議における印鑑証明書に代わる書類ですので、より証明力が高い「形式1」で受け取る必要があるので、注意してください。
以上、本日は、海外に居住している相続人と印鑑証明書について解説していきました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
3か月経過後の相続放棄について
お久しぶりです。
弁護士の林です。
肌寒い季節になってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、3か月の期間経過後の相続放棄の可否についてお話していこうかなと思います。
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内(この3か月間を「熟慮期間」と言います。)に行わなければならないとされています。
そして、この期間内に相続放棄をするか否かを決定することができない時は、相続放棄の申述期間の延長を申し立てる事ができるとされています。
この時、3か月や延長後の申述期間を経過してしまった場合には、一切相続放棄を行う事はできないのかが問題となります。
この点について、参考になる判例として、最判昭和59年4月27日があります。
この判例では、被相続人の連帯保証債務の存在を全く知らなかった相続人について、相続開始後1年後に債務を知った場合に、相続放棄が認められるのかが問題となりました。
最高裁は、熟慮期間が定められている趣旨は、熟慮期間があれば、被相続人の債権債務関係を調査することができるという点にあるとしました。
そのため、最高裁は、3か月以内に相続放棄等を行わなかった理由が「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、相続放棄を認めるべきであるとしました。
このように、債務の存在を知った経緯によって、相続放棄が認められる場合があるのです。
そのため、相続放棄の申述期間が経過した後に、債務の履行を請求された場合でも、一度弁護士に相談することが良いです。
認知請求と放棄を約束する契約の有効性
皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
まだまだ暑い日が続きますね。
本日は、認知請求と認知請求を放棄する契約の有効性についてお話していきたいと思います。
1 認知請求とは、父親が子供との法律上の親子関係を認めない場合に、子が父親に対して法的父子関係を認めるように請求する権利のことを指します。
この時、父親としては、法的親子関係を認められてしまうと、養育費の支払い義務や、相続権が発生してしまうので、それらを回避するために認知請求を避けたいと考える場合があります。
その方法として、いくらかの金銭を子供や母親に渡して、認知請求権を放棄してもらう契約を行うという場合があります。
このような契約は、そもそも契約として有効なのでしょうか。
2 この点について、判例・通説は、このような契約は無効であると考えています。
根拠としては、父との父子関係が認められることが、基本的に子供の利益となる点や、このような契約を認めると少ない金額で放棄の契約がされてしまうおそれがあって子供の利益に適合しないという点が挙げられています。
もっとも、子供の利益を十分に確保した場合には有効となるという考え方もあるので、これからの裁判例に注目する必要があるでしょう。
3 では、既に放棄の契約を行っていた場合には、どのようになってしまうのでしょうか。
例えば、父から多少のお金を渡されて契約書に押印を行っていた場合にはどのような処理となるのでしょう。
この場合、子供としては、父親に対して、認知請求を提起することができます。
上述のとおり、認知請求の放棄をする契約は無効であるため、当然の帰結といえるでしょう。
では、契約の際に支払った金銭については、どのように処理するのでしょうか。
この処理方法の一つとして、父親から子供に対して不当利得返還請求として、支払った金額の返還を求めるという解決が考えられます。
もっとも、このような不当利得返還請求については、「父子関係を認めない」という信義則上許されない原因で渡したお金なので、返還が認められないという考え方や、養育費の一部として理解して返還を認めないという考え方があるため、注意をしましょう。
4 このように、認知請求を放棄する契約に関しては、様々な考え方が指摘されているところです。
そのため、少しでも疑問に思ったことがある場合には、お近くの弁護士に相談するようにすると良いでしょう。
それでは、また次回お会いしましょう。
遺言書で生命保険金の受取人を変更する方法と裁判例
お久しぶりです。
弁護士法人心、弁護士の林です。
皆様はどのようにお過ごしでしょうか。
私は、先日、豊田の鞍ヶ池公園までドライブに行きましたが、暑すぎたので早々に帰宅してしまいました。(笑)
さて、今回は、生命保険の受取人を遺言書で変更する方法とその記載方法について、解説していきたいと思います。
1 原則
まず、そもそも保険金の受取人を遺言書で変更することは可能なのでしょうか。
この点、保険法44条1項は、
「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」
と規定しています。
そのため、遺言書によって保険金の受取人を変更することは可能なのです。
但し、同条2項は、
「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」
と定めています。
この規定により、例え遺言書で受取人の変更を行ったとしても、保険会社が先に元の受取人に保険金を支払っていた場合には、保険会社に対して責任追及を行っていくことはできないということになります。
相続人の方は、この規定に注意を払って、なるべく早期に行動するように心がけることが重要でしょう。
2 遺言書の記載方法
では、遺言書で受取人の変更を行う場合には、どのような記載方法を取ればよいのでしょうか。
ここでは、一般的に推奨される方法と裁判例から見る傾向を見ていきましょう。
ア 一般的に推奨される記載例
一般的に、遺言書で保険金の受取人を変更する場合には、できる限り以下の要素ごとに特定して記載することが望ましいとされています。
①証券番号
②保険会社名
③契約締結日
④保険契約者
⑤被保険者
⑥受取人
この6つの要素で、なるべくどの生命保険の受取人を変更するのかについて疑義が入らないようにすることが重要であるとされています。
このことから、記載としては、
「遺言者は、下記に記載する生命保険契約の受取人をAからBに変更する。
記
①証券番号 ○○-○○-○○
②保険会社名 ABC生命保険
③契約締結日 令和6年8月20日
④保険契約者 遺言者
⑤被保険者 遺言者
⑥受取人 遺言者の妻・A 」
等と記載するのが良いでしょう。
イ 裁判例
もっとも、必ずこの記載方法でないと受取人の変更が認められないというものではありません。
なぜなら、上記の保険法では、遺言書の書き方について法定されているわけではなく、遺言書は本来、その記載文言から、遺言者の意思を解釈していくことができるからです(「遺言書の形式的な記載だけでなく、遺言者の状況等からその真意を探求していくべきである」とした判例として、最判昭和58年3月18日があります。)。
そして、裁判例でも、生命保険の契約者兼被保険者である遺言者が「一切の財産をAに相続又は遺贈する」(原文と相違がある可能性があります。)という趣旨の遺言書を残した事案で、この遺言書から生命保険の受取人を変更することを認めた裁判例(京都地判平成18年7月18日)があります。
この裁判例では、形式的に受取人となるのは遺言者の子供でしたが、遺言者が遺言書を作成した当時、遺言者と子供は疎遠であり、電話や訪問を受けていなかったこと、遺言者が遺言書を作成したのはAの自宅で療養を受けた恩義に報いる趣旨であったことから、遺言者の意思としては、保険金を含む全ての財産をAに渡す意思であったとされたのです。
ウ まとめ
このように、生命保険金の受取人の変更に関して遺言書を記載する場合には、なるべく特定して書くことが望ましいものの、形式的に変更の意思が書かれていなくても、実質的に変更を認める余地があります。
そのため、保険金の受取人について疑義がある場合には、弁護士に相談するようにすると良いでしょう。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
生命保険金の受取人について
皆様、お久しぶりです。
弁護士法人心の弁護士の林です。
最近は、気温が高く寝苦しいですね。
皆様も体調にはお気を付けください。
今回は、生命保険の受取人が、被保険者の死亡以前に死亡していた場合の生命保険の受取人について解説していきたいと思います。
まず、生命保険契約を締結した際の受取人は、基本的に「戸籍上の配偶者又は2親等以内の親族」とされていることが多いです。
このように受取人が限定されている趣旨は、生命保険が、残された親族の生活を守っていくためのものである点にあります。
では、この時に受取人が被保険者より先に死亡していた場合には、誰が受取人となるのでしょうか。
この点について、保険法46条では、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」とされています。
例えば、被保険者と配偶者の間に子A、B、Cの3人がいる場合に、Aが受取人と指定されていたが、Aが先に死亡し、被保険者がその後に亡くなったという事案について考えてみます。
この時、Aに配偶者と子供がいる場合には、Aの配偶者と子供がAの法定相続人となりますので、Aの配偶者と子供が生命保険の受取人となります。
さらに、Aには配偶者しかいない場合には、Aの法定相続人はAの配偶者と被相続人の配偶者となりますので、Aの配偶者と被相続人の配偶者が受取人となるのです。
このように、生命保険金の受取人が先に死亡してしまった場合には、意図していない方に生命保険金が渡ってしまうことがあります。
では、意図していない方に生命保険金が渡らないようにするための方法は無いのでしょうか。
この点、一つの方法として、遺言書で受取人の変更を指定しておくという方法が考えられます。
まず、保険法44条1項にて「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」とされています。
この規定を使用し、遺言書にて「保険金受取人が被相続人の死亡以前に死亡していた場合には、遺言者を被保険者とする下記の生命保険の受取人を、○○から○○に変更する。」と定めておくことで、意図していない方に生命保険金が渡らないようにすることができます。
例えば、上記の事例では、生命保険の受取人Aが先に死亡していた場合には、その受取人をBに変更すると指定することで、意図していない方に保険金が渡らないようにすることができます。
そのため、生命保険契約を結ばれている場合には、受取人の対策として遺言書を使用することも検討しておくと良いでしょう。
但し、この方法を使用する際には、
①受取人となる人に、被相続人が死亡した際には、受取人の変更を生命保険会社に通知する必要があること(保険法44条2項)を事前に知らせておくこと
②変更先となる受取人が生命保険契約の受取人として指定できる範囲内であるかを生命保険会社に確認しておくこと
を忘れずに行ってください。
では、また次回のブログでお会いしましょう。
預貯金の取引履歴の取得と
お久しぶりです。
弁護士の林です。
皆様はいかが過ごされていますでしょうか。
今回は、銀行が預貯金口座の取引履歴の開示請求に対して拒否することができるのかという点について解説していきたいと思います。
相続の事案では、被相続人の預貯金口座から相続人の一人が多額の出金をしているという場合があります。
その場合、他の相続人としては、預貯金の管理状況を把握するために、預貯金口座の取引履歴を取得する必要があります。
この時、金融機関は、被相続人のプライバシーを侵害するから取引履歴を開示しないという回答をすることが許されるのでしょうか。
平成21年1月22日最高裁判例は結論として、金融機関は原則として取引履歴を開示しなければならないと判断しました。
これは、
① 預金者は、金融機関の事務処理が適切になされていることを確認するために取引履歴の開示を求める事が必要不可欠であること
② 取引履歴の開示の相手方が共同相続人である限り、プライバシーを侵害し、金融機関の守秘義務違反が問われることは無いこと
の2点を理由としているみたいです。
ただし、取引履歴の開示が「開示請求の態様、開示を求める対象ないし範囲等によっては、預金口座の取引履歴の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合がある」と判断されている点に注意が必要です。
例えば、金融機関に対して預貯金口座の取引履歴を30年分開示しろという請求を想定しているものと考えられます。
上記の例との関係でいえば、被相続人の口座から多額の引き出しがあったとしても、被相続人が預貯金通帳を管理できなくなったのが5年前くらいからであるのであれば、その期間に対応した取引履歴を取得するべきであるということです。
必要以上の取引履歴の取得については、金融機関も拒否することができる場合があり得るのかもしれません。
以上より、皆様も、取引履歴の取得を拒否された場合には、諦める前に弁護士に相談してみるのが良いかもしれません。