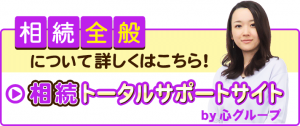少年事件の手続きについて
みなさま、こんにちは!
今回は、少年が逮捕・勾留されている場合の少年事件の手続きについて解説していきたいと思います。
少年が逮捕・勾留されている場合の少年事件の手続きには、大きく分けて3つの段階が考えられます。
その段階とは、①逮捕、勾留段階②家裁送致段階③審判段階です。
①の逮捕、勾留段階では、成年の刑事事件と同様に、逮捕から72時間以内に検察へと送致され、勾留手続きが行われた場合には原則10日間の身体拘束が行われることになります。
この逮捕、勾留段階では、警察官や検察官から事件に関する取り調べ等の捜査が行われる事になります。
少年はこの間に警察の留置施設もしくは少年鑑別所に身体拘束されることになるため、心身に大きな負荷がかかることになります。
そのため、弁護人やご家族の方(面会が許可されている場合)が定期的に会いに行くことでそのストレスを和らげる必要があります。
②の家裁送致段階では、家庭裁判所の調査官による面接が行われることになります。
検察は、少年事件については、原則として全件を家庭裁判所に送致することとされています(全件送致主義)。
全件送致主義が取られている背景としては、非行を行った少年はたとえ軽微な犯罪であったとしても、重大な犯罪を行ってしまう危険性があることに鑑みて、裁判所が後見的に少年に潜む問題点を指摘し、更生を行っていく必要があると考えられている点にあります。
一定の軽微な犯罪については、調査官による面接も行われない「簡易送致」という類型もあるものの、ほとんどの事件は家庭裁判所に送致されます。
この調査官による面接では、少年の非行に関する事実のみではなく、少年の養育環境や思考に関する傾向なども調査されることになり、そこで調査された事実が裁判官に報告され、審判の前提となるので、とても重要な手続きであるといえます。
③の審判段階では、裁判所が少年に対して、⑴保護観察⑵少年院送致⑶不処分、審判不開始決定のいずれかの決定を行います。
審判手続きを行う前に裁判所から審判期日が設定され、その期日において、裁判所から少年や親族に対する質問が行われます。
この段階では、裁判所が審判を下すうえで重要な質問が行われるため、付添人を選任して対策を行っておくことが望ましいです。
この審判期日でも、非行事実に関する質問のみでなく、養育環境等に関する質問までも行われるため、少年のみではなく、親族の方も今後どのように少年を養育していくのかについて考えておく必要があります。
このように、少年事件の手続きは、少年の今後の更生を考えていく構成となっているため、当事者全員が少年の今後の更生を考えておくことが望ましいといえるでしょう。
それでは、今回はここで失礼いたします。